大学入試の小論文では、「命」「倫理」といったテーマが頻出です。
とくに医療系・福祉系・看護系・教育系・心理系の学部では、ほぼ毎年どこかの大学で「生命の尊重」「医療倫理」「生と死」「安楽死」「臓器移植」などの問題が出題されています。
これらのテーマは、単に「正解・不正解」で語れるものではなく、受験生一人ひとりの「価値観」や「考える力」が問われる分野です。
だからこそ、文章構成や論理展開を明確にして、自分の立場を丁寧に表現することが重要になります。
この記事では、「命・倫理」をテーマにした小論文を書く際の基本的な考え方、構成の作り方、練習法までを、順を追って解説します。
1.命・倫理テーマの小論文で問われる力
まず、このテーマで大学が見ているのは、次の3つの力です。
-
価値観の整理力
生命や倫理に関する問いに対して、「自分はどう考えるか」を自覚し、筋の通った立場を取れるかどうか。
感情的な意見ではなく、理由を伴う判断が求められます。 -
多面的な思考力
命や倫理の問題には、「個人の権利」「社会全体の利益」「科学技術の進歩」「宗教・文化的背景」など、さまざまな観点があります。
一つの立場だけでなく、対立する考え方も理解したうえで、自分の意見を整理することが大切です。 -
論理的表現力
文章の流れが明確で、誰が読んでも理解できる構成になっているかどうか。
倫理問題ほど感情的に流れやすいテーマはありません。だからこそ、「感情よりも論理」で書く姿勢が必要です。
2.命・倫理テーマでよく出る具体的課題
命や倫理を扱う小論文では、次のような具体的な課題が出題されます。
-
安楽死・尊厳死に関する是非
-
臓器移植における提供の意思と家族の判断
-
出生前診断の倫理的問題
-
医療と経済のバランス
-
動物実験・AI医療の倫理
-
感染症対応における人権と公共の利益
-
教育現場での「いのちの授業」や命の尊重教育
どの課題にも共通するのは、「人間の尊厳をどう考えるか」という根本的な問いです。
そのため、受験生は「自分の中の価値観」を整理しながら、「他者の考えも理解する姿勢」を持って書くことが求められます。
3.命・倫理テーマの小論文の構成パターン
このテーマでは、感情に流されず、論理的に構成することが重要です。
おすすめの構成は以下の4段階です。
【構成例】
①問題提起 → ②対立の整理 → ③自分の立場と根拠 → ④まとめ・提言
① 問題提起
最初に「社会で何が問題となっているのか」を客観的に説明します。
例:
近年、医療技術の発達により、人の生命をどこまで延命させるべきかが議論されている。
とくに安楽死や尊厳死をめぐる問題は、「生きる権利」と「死ぬ権利」という二つの価値が対立している。
ここでは、自分の意見をいきなり書くのではなく、「社会的背景」を冷静に述べるのがポイントです。
② 対立の整理
次に、異なる立場の意見を簡潔に紹介します。
例:
安楽死を容認する立場は、「本人の苦しみを取り除く人間的な選択」と考える。
一方で、反対する立場は、「生命はどのような形でも尊重されるべきだ」と主張する。
この部分では、両方の主張を「公平に」整理しましょう。ここで偏りすぎると、説得力を欠きます。
③ 自分の立場と根拠
ここが小論文の中心部分です。
例:
私は、安楽死を一律に認めることには慎重であるべきだと考える。
なぜなら、本人の意思を確認することが難しいケースや、家族・医療者への圧力が生じるおそれがあるからだ。
ただし、十分な説明と本人の明確な意思が確認される場合には、例外的に尊厳死を認める制度づくりは必要だと思う。
このように、「原則」「理由」「具体例」を組み合わせて書くと、筋の通った意見になります。
④ まとめ・提言
最後は、「自分の意見を社会にどう生かすか」で締めくくります。
例:
科学や制度が発展する中でも、最終的な判断の基準となるのは人間の尊厳である。
命のあり方について、社会全体で対話を続けていく姿勢が求められる。
4.文章を感情的にしないためのコツ
命・倫理のテーマでは、「かわいそう」「仕方ない」など感情的な表現が出やすいですが、試験では避けましょう。
次のように「論理的に言い換える」練習が効果的です。
このように書き換えることで、文章全体が落ち着いた印象になり、採点者にも「考えの深さ」が伝わります。
5.「命・倫理」小論文でのNGパターン
次のような書き方は減点対象になりやすいので注意しましょう。
-
感情的な主張に偏る(「私は絶対に許せない」「絶対に間違っている」など)
-
具体例がない(自分の考えだけで根拠が示されていない)
-
他人の考えを否定するだけ(対立意見を理解しようとしていない)
-
専門用語の誤用(例:「尊厳死」と「安楽死」の混同)
「命」を扱うテーマでは、“慎重で誠実な書き方”が求められます。
自分の考えを貫くことは大切ですが、他者の考えを否定する書き方は避けましょう。
6.練習法:ニュース・エッセイを題材に考える
命・倫理のテーマは、抽象的な言葉だけではイメージしにくいものです。
そこでおすすめなのが、「ニュース」や「エッセイ」を題材にした練習です。
① 時事問題を整理する
新聞やニュースサイトで、「医療倫理」「高齢者介護」「AI医療」「臓器提供」などの話題を調べ、
「どんな対立があるか」「自分ならどう考えるか」をノートにまとめましょう。
② 300字でまとめる練習
いきなり600字や800字で書くのは難しいので、まずは300字で「自分の意見+理由」を書く練習から始めると良いです。
③ 他人の意見を読む
学校や予備校の模範解答、評論文の文章などを読むと、「論理的な書き方」の感覚がつかめます。
とくに、「対立→折衷→提言」の流れを意識して読むと構成力が伸びます。
7.命・倫理のテーマで差がつくポイント
最後に、合格レベルの小論文とそうでない小論文の違いをまとめます。
8.まとめ:命のテーマは「正解」を書くものではない
命や倫理の小論文に「正解」はありません。
大切なのは、「自分の考えを、社会や他者の意見の中でどのように位置づけるか」です。
医療や教育、福祉を志す人ほど、命に関わる判断を避けずに考える力が求められます。
小論文はその第一歩です。
テーマに向き合う中で、「自分が何を大切にしたいのか」を整理することこそが、学びの本質につながります。

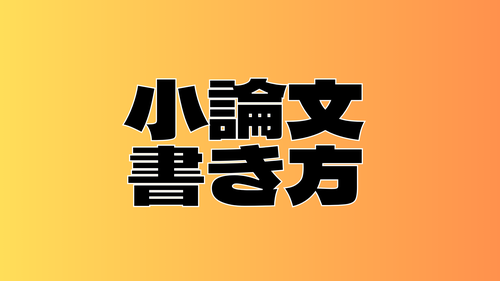


コメント (0)