共通テストの現代文は、「何となく読んで、何となく答えたら外れる」科目です。
数学や英語のように「正解が明確ではない」と感じて苦手意識を持つ受験生も多いでしょう。
しかし、現代文は決して「センス」や「感覚」で解く科目ではありません。
構造を理解し、根拠をもって読み進めれば、誰でも安定して点を取れるようになります。
この記事では、現代文が苦手な人が最初にやるべき「3つのこと」を、共通テストの出題傾向に沿って具体的に解説します。
勘や感情に頼らず、“論理的に読む習慣”をつくることが、現代文克服の第一歩です。
1.【第一のステップ】「主張・理由・具体例」の三要素を見抜く
現代文の読み方の基本は、文章を「構造」でとらえることです。
特に評論文では、「筆者の主張(言いたいこと)」「理由(なぜそう言うのか)」「具体例(それを示す実例)」の三つで構成されています。
この三要素を区別せずに読んでしまうと、どの部分が重要なのか分からなくなり、設問に答えるときの根拠も見失います。
たとえば次のような段落構成を意識してみましょう。
-
主張:筆者が一番伝えたいこと。段落の冒頭または末尾に現れやすい。
-
理由:主張を支える論理。「なぜなら」「したがって」などの接続語に注目。
-
具体例:主張や理由をわかりやすく説明する部分。人物名や固有名詞が出てくるのが目印。
この三つの関係を整理しながら読むだけで、文章の「どの部分を重視すべきか」が明確になります。
★練習法
市販の現代文問題集を使うときは、段落ごとに「主張」「理由」「具体例」をマーカーで色分けしましょう。
自分の読解の中で筆者の意図を明確に「見える化」する習慣をつけると、設問で迷うことが減ります。
2.【第二のステップ】「対比」と「因果」を追う
共通テストの現代文は、論理構造を理解しているかを問う問題が多いです。
その中でも、筆者の立場をつかむカギとなるのが「対比」と「因果」の関係です。
■ 対比を見抜く
筆者が主張を強調するために、しばしば「AとBを比較してどちらが正しいか」を示します。
たとえば次のような文章構成です。
「昔の教育は暗記中心であった。しかし現代では、思考力を重視する教育が求められている。」
このとき、筆者の立場は明確です。「昔」よりも「現代」の教育を肯定している。
つまり、「対比のどちら側に筆者が立っているか」を判断することで、選択肢の正誤も見抜けるようになります。
■ 因果関係を追う
もう一つの鍵は「原因」と「結果」のつながりです。
現代文では、「なぜそうなるのか」「その結果どうなったのか」をつかむことで、内容を深く理解できます。
例:「情報があふれすぎた結果、かえって人々は判断力を失った。」
この文では、「情報があふれた(原因)」→「判断力を失った(結果)」という構造。
共通テストではこの因果の流れを問う設問が多く、「理由として最も適切なものを選べ」といった形で出題されます。
★練習法
文章を読むとき、
-
「しかし」「ところが」「反対に」→対比のサイン
-
「だから」「そのため」「結果として」→因果のサイン
を見つけたら、ノートに矢印(→)で関係をまとめましょう。
目で追うだけでなく、図式化して整理することで、論理の流れが一目で理解できるようになります。
3.【第三のステップ】「設問の根拠」を本文で探す習慣をつける
現代文の最大の特徴は、「すべての答えが本文の中にある」ことです。
これは、英語の長文読解と同じ原則です。
にもかかわらず、多くの受験生が「なんとなくの印象」で選択肢を選んでしまいます。
たとえば「筆者の気持ちはどれか?」という問題で、「この人は怒ってそうだから②かな」と勘で答えてしまう。
こうした読み方をしている限り、現代文の得点は安定しません。
■ 根拠の位置を明確にする
選択肢を選ぶ前に、必ず「この内容が本文のどこに書かれていたか」を確認しましょう。
本文中の一文を指でなぞって、「ここが根拠になる」と説明できるようにするのが理想です。
この「根拠の明確化」を習慣化すれば、選択肢の迷いが大幅に減ります。
■ 典型的なミス例
-
設問が問う部分より前後を読み落とす
-
「筆者」と「引用文」の立場を混同する
-
「反対意見」を筆者の意見と誤解する
こうした誤読は、すべて「根拠確認の不足」から生じます。
現代文は「本文の論理を再構築する作業」と考えると、感覚ではなく理屈で答えを導けるようになります。
★練習法
過去問や模試の復習では、間違えた問題を「根拠探し」に変えましょう。
-
自分が選んだ選択肢の根拠は本文のどこか?
-
正答の根拠はどこか?
-
その二つはどんな違いがあったか?
これを丁寧に分析するだけで、「どういう読み方をすれば正答にたどり着けるのか」が感覚的に掴めてきます。
4.共通テスト現代文の特徴を理解する
共通テストの現代文は、「知識ではなく思考力を問う」試験です。
評論・小説・実用文(資料読解)と、異なる種類の文章が出題されますが、どれも情報を整理し、根拠を持って判断する力を求めています。
評論では論理構造、小説では人物の心理変化、資料文では要約力が問われます。
しかしいずれも「文中の根拠を探して選択する」という本質は同じです。
現代文を苦手とする人は、この「根拠探し」を後回しにしてしまいがちです。
まずはどんな文章でも「主張・対比・因果・根拠」という4つの視点で読み進めることが、点数アップへの近道です。
5.文章を読む前に「問いの意識」を持つ
現代文が苦手な人ほど、本文を読むときに「目的意識」を持たずに読み始めてしまいます。
しかし、設問を先に読むだけで読解の方向性が定まり、必要な情報に集中できます。
たとえば「筆者の主張として最も適切なものを選べ」という設問なら、読むべき部分は筆者の意見が書かれた箇所。
「具体例の意図を問う」なら、例が出てきた段落に注意すればよい。
このように、「何を問われるか」を意識して読むと、情報を取捨選択できるようになります。
読解スピードも上がり、共通テストの限られた時間内でも安定した読解が可能になります。
6.復習こそ現代文の本番練習
現代文で伸び悩む人の多くは、問題を「解いて終わり」にしてしまいます。
しかし、現代文は復習こそが本当の勉強です。
解いた後は、必ず次の3点を確認してください。
-
どの設問で根拠を誤ったか
-
どの接続・対比表現を見落としたか
-
筆者の立場をどう誤解したか
この反省を積み重ねることで、自分の「読みグセ(誤読のパターン)」が見えてきます。
たとえば、「いつも具体例の部分で間違える」「逆接のあとの主張を軽視してしまう」など、自分の癖を自覚できれば、次から修正が可能になります。
7.まとめ:「根拠に基づく読解」が現代文克服の鍵
現代文が苦手な人が最初にやるべきことは、次の3つです。
-
「主張・理由・具体例」の三要素を整理して読む
-
「対比」と「因果」の流れを追って、筆者の立場をつかむ
-
「根拠」を本文から探し、感覚ではなく論理で選ぶ
この3つを意識するだけで、現代文の見え方は劇的に変わります。
感覚的な読解ではなく、「本文のどこに根拠があるのか」を意識した読み方を続ければ、共通テストの現代文は安定して高得点を取れるようになります。
「現代文が苦手」というのは、センスがないからではなく、読むときの“意識の置き方”が間違っているだけです。
構造をつかみ、論理で読む。
これが、現代文を得点源に変えるための最初の一歩です。

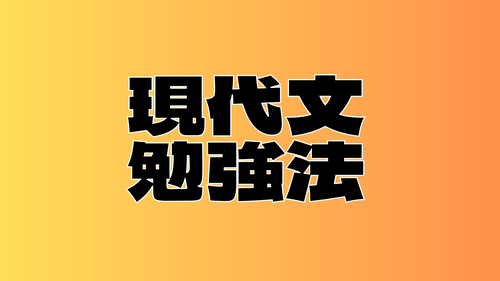


Comments (0)